ジュリーの運命が急速に動き出す、取り返しのつかない祭の一夜!
作品について
『令嬢ジュリー』は、フランス現代演劇界でもっとも注目を集める演出家の一人フレデリック・フィスバックを演出にむかえ、満を持してお届けする、この秋のSPACの新作です。奔放なお嬢様ジュリーと召使いジャンの階級を越えた秘め事が、一年でもっとも日のながい夏至祭の夜を舞台に、夢と現実のはざまで揺れ動く二人の会話を中心に描かれます。いつのまにか後戻りできないところまで来てしまったジュリー…。彼女が最後に選んだ意外な結末を、あなたは直視できるでしょうか!?
あらすじ
夏至祭の前夜。令嬢ジュリーは台所にいる召使いジャンのもとを訪れる。ジャンには同じく召使いのクリスティンという許嫁がいたが、ジュリーはお嬢様としての特権を行使して、ジャンに自分を楽しませるように強要する。二人はダンスを踊ったり、お酒を飲んだり、しばし愉快な時間を過ごすのだったが、昔から憧れていたと口説くジャンにのせられたジュリーは、情事におよんで・・・。
フレデリック・フィスバック インタビュー
--作品の背景をお聞かせください。
この作品は19世紀末に書かれています。西洋にとって重要な時期です。清教徒の厳格な考え方が蔓延し、同時に経済的な大発展が起きたころです。現代における資本主義的なシステムが導入された時期と考えられます。本当に少数の人々が富を蓄え、彼らが大多数の人々から搾取する仕組みです。この経済的な大発展は西洋では同時に、人間主義的そして政治的なユートピア思想とともに現れています。こういったものは政治的な潮流として20世紀前半を支配してゆくものになっていきます。特に共産主義や、大衆的なものとして台頭してきた社会主義など、多くの考えが生まれました。
このユートピア思想はいくつかのキーワードを扱っていました。男と女の間の平等、すべての人間の平等、それから衛生主義、これはすべての人が医療や知識にアクセスできなければいけないという考え方です。ストリンドベリはこういう時代にこの作品を書いています。
--登場人物はどういう人たちでしょうか。
まず貧しい男性が出て来ます。彼は平民の出ですが、平民にしてはのぼりつめた男で、これ以上のぼることができないところまで来ている男です。このジャンは新興富裕層になろうとしています。自分の知力活力を使って出世します。しかし、これ以上の地位にのぼるためには起業家になることが必要で、資本がないので起業できずにいるのです。そして若い令嬢がいます。非常に育ちがよく、2週間前に婚約破棄をむかえて動揺しています。この女性は矛盾を孕んだ教育をうけてきた人です。彼女のお母さんはフェミニスト思想をもっていて、男女平等や世間的な慣例に反する考えをもっています。子供を産むということについても反発していて、偶然できた子供としてこの主人公は出てくるわけです。そしてかなり保守的なお父さん。彼は貴族で、大変裕福な人です。オープンな考え方の人でしたが、自分の社会階級のなかでかんじがらめになっています。つまり、ジュリーは裕福だけれども不安定な環境のなかで育っています。しかもジュリーが作品に登場するのは、人生において、動揺の大きい、弱っている時期です。というわけで、この作品がはじまるとき、ジュリーもジャンも行き止まりの状態にはまっています。
--この作品は現代日本にもつながるものがあると思いますが、いかがでしょうか。
私にとって、現代の雇用者と被雇用者との関係は、作品の主人と召使いの関係で考えられます。私は日本社会に詳しいわけではありませんが、演劇界の知人と話していると、ロストジェネレーション世代の人は、両親が戦後の経済的な大発展を支えたことや日本社会というものが今の時代まで建て直されたという流れに疑問をなげかけた人たちでもあるだろうと思います。両親の世代のように、会社に入って、自分の生活や家族を犠牲にしてきた人たちに対して、問いかけをしたのだという風に理解しています。
失業という問題が裕福な社会において問いかけられていますが、これは単純な問題ではないと思います。職を選ぶことは人生との関係を選ぶことになりますので、この会社に25歳で入って65歳までこのなかにいていいのか、私の人生はこれでいいのかという問いかけでもあります。多くの若い世代が感じている疑問だと思います。この問いかけはやっかいな問題である「私のアイデンティティは何か」という問題につながってきます。
--作者のストリンドベリはこの作品で何を表現しようとしたのでしょうか。
社会的な疑問、経済的な疑問を越えて、なにが世界を動かせるのかといえば恋愛感情であったり、欲望であったりする、とストリンドベリが提示しているようにも思えます。演劇における大きな問いかけはこれに集約されるのかなと思いますが、死と生と愛というものではないのか、ということが見えて来ます。この作品のなかで何が悲劇的かと言えば、登場人物は展望がみえない。ひとりでは展望がみえない。ふたりでやっと展望が見えているときもあるのですが、ふたりが波長をあわせることができない、コミュニケーションをとることができないことが描かれていると思います。ときに本心からふたりで建設的に生きて行こうと思うのですが、それができない、ということが描かれています。
演出家、そして俳優も同じ思いがあるんじゃないかと思いますが、私たちには隠れた野望、隠れた希望があって、公演を見に来た人のうちの誰かの人生の辛さを緩和できればという希望です。ほんの小さなことでそういうことは起きうると思っています。ジェラール・ド・ネルヴァルも、自殺した晩、パリの夜をさすらって歩いていたんですが、誰かに話をしに行きたいと感じて、劇場へ行ったんですけれど扉が閉じていた、ということがあったらしいのです。その翌朝、パリの橋の下で首を吊っているのが見つかったんです。もしその扉が閉じていなかったらそういうことは起こらなかったかもしれない。ほんのちょっとのことで物事は変わりうるだなと思います。


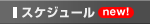





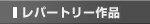


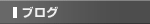

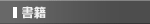
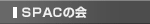
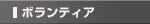




 演出家。1966年生まれ。パリ国立高等演劇学校(コンセルヴァトワール)に学んだ後、ジェラール・フィリップ劇場(サン=ドニ)、ナンテール・アマンディエ劇場で、俳優、演出家として活躍。代表的な演出作品に『マリアへのお告げ』『東京ノート』『ソウル市民』『ベレニス』『屏風』『舞台は夢』オペラ『アグリッピーナ』など。2002年よりパリ近郊のステュディオ・テアトル・ド・ヴィトリーのディレクターに就任。07年度アヴィニョン演劇祭の提携アーティスト。06年〜10年2月、新たな芸術・文化創造の試みの場としてパリ市に設立された「スタジオ104」で初代ディレクターを努めた。フランス現代演劇で最も注目される演出家のひとりである。
演出家。1966年生まれ。パリ国立高等演劇学校(コンセルヴァトワール)に学んだ後、ジェラール・フィリップ劇場(サン=ドニ)、ナンテール・アマンディエ劇場で、俳優、演出家として活躍。代表的な演出作品に『マリアへのお告げ』『東京ノート』『ソウル市民』『ベレニス』『屏風』『舞台は夢』オペラ『アグリッピーナ』など。2002年よりパリ近郊のステュディオ・テアトル・ド・ヴィトリーのディレクターに就任。07年度アヴィニョン演劇祭の提携アーティスト。06年〜10年2月、新たな芸術・文化創造の試みの場としてパリ市に設立された「スタジオ104」で初代ディレクターを努めた。フランス現代演劇で最も注目される演出家のひとりである。