『ドン・キホーテ』も記憶に新しい原田一樹演出作品、
待望の再演!
作品について
末摘花は、美男美女がてんこもりの源氏物語において、たぐいまれな不美人として登場する姫。その醜い顔立ちと不器用な振る舞いは光源氏もあきれるほどでしたが、源氏を慕う心は誰よりも純真で、晩年は源氏の寵愛を受けました。この『しんしゃく源氏物語』では、逢瀬の後、待ち続ける足が遠退いた源氏をただただ一途に待ち続ける末摘花の姿が描かれます。不器用で醜い姫の思慕、その儚さと美しさが際立つなか、そんな姫に翻弄される侍女たちの様子がユーモラスに展開します。原田一樹によって躍動感溢れる舞台に仕上げられた『しんしゃく源氏物語』、待望の再演をお見逃しなく!
あらすじ
末摘花の御殿。末摘花は古風な教育を受けた頑固で一途な姫。光源氏を慕う心は強く、いつ戻ってくるのかもわからない源氏のことばかり思って暮らしている。そのせいで世間から見放されてしまった感のあるこの屋敷はボロボロで、食事も質素、没落が目に見えるような有様。そんな生活に耐えかねて、今日もまた一人、侍女がこの屋敷を逃げ出す。残された侍女たちは気が気でないが、末摘花は彼女たちを尻目に泰然自若として騒がず、今日も源氏のことを想っている。源氏は必ずもどってくる、と。一体いつ、本当にもどってくるのだろうか…。
原田一樹 インタビュー
久々の再演にのぞむ演出家・原田一樹は、今、何を考えているのだろうか…
−−このたび『しんしゃく源氏物語』を再演する運びとなりました。SPACで繰り返し上演されてきた本作でが、これまでお客様の反応はいかがでしたか?
この作品はかつて、新劇のある大ベテランの女優さんに紹介していただいて、その方のグループで87年に演出したのが最初です。作者の榊原政常さんも齢90を超えられてご存命だったと記憶しています。SPACでは98年と99年に野外劇場『有度』で男性によるキャストで上演しました。その後当時の鈴木忠志監督の下で女性版という本来の形に戻して、オーソドックスなスタイルの今のSPAC版「しんしゃく源氏物語」になりました。それ以来静岡での中学生鑑賞事業を数多く続け、上演回数はもちろん最多で、SPACに育てられた舞台だと実感しています。それだけに、あらゆるパートにおいての客席の反応も意識しているつもりなのですが、やはり毎回新鮮な出会いはあります。一昨年の上演の際も、観客の中には何回か見て下さっている方もいらして、とてもよい雰囲気に包まれていると感じました。
−−前回の上演から2年が経ち、さらにパワーアップした『しんしゃく源氏物語』が期待されますが、再演にあたって特に力を入れたいことは何ですか?
今回はキャストも半分近くが入れ替わります。舞台という場所は、やはり俳優の生活史も投影される空間だと思っています。演出はまず俳優一人ひとりの価値観と出会い、せめぎ合い、その上で刺激的で劇的な時間を紡がなければなりません。新しい出会いを大切にしたいと感じています。そして何よりも、普遍的なテーマである、人が人を想うということ、この根本に立ち返りたいと考えています。
−−SPACでは『しんしゃく源氏物語』のほかに『ドン・キホーテ』も演出されている原田さんですが、SPACで仕事をされるときに感じることがあればお教えください。
まず第一に、稽古場や宿舎の整備された創造環境のすばらしさ。ただ劇場という場所があるのではなく、ここに同じ創造に身を粉にして立ち向かう仲間がいるという心強さ。それを地域が支えているという実感の中で仕事が出来る緊張と誇り。そして、作品への反応や感想に生で触れられる実感、これは地域だからこそのもので、この交流こそ演劇に限らず、現代の私たちに必要な、地味ですが生で緊密で刺激的な交流だと感じています。
−−『しんしゃく源氏物語』でも『ドン・キホーテ』でも一途な思いでひた走る人物が主人公になっています。演劇でこうした人物を描くことの面白さを教えて下さい。
ドラマというのは、やはり葛藤なんです。ひた走る人物というのは、決して何も見ず何も考えずにただ自分の欲望に従う人物ではありません、むしろ、何かをしなくてはいけない、何かをしたいと本気で考えている人物ほど、さまざまな障害や、周りで起こることに敏感で、葛藤も本気の度合いが強いほど深くなるのです。この葛藤をどのような目に見える形にして、あるいは想像できる物にして舞台に描こうか、と考えることが演出の喜びの一つでもあります。そして、そういう演出の意図すら裏切って自由に奔放に飛び回る人物の首根っこを捕まえられるか、それともこちらが翻弄されるか、その丁々発止は創造過程の醍醐味です。
−−本公演は鑑賞事業として多くの中高生にご覧頂きますが、演劇と若者の理想的な関係とはどういうものでしょう?
ワークショップや高校演劇、市民劇団とのかかわりの中で、私自身も若い人たちと多く付き合います。これは私たち以降の世代には、たとえ演劇を目指す者たちでももう当たり前のことですが、演技というものは圧倒的にテレビで見ているんですね。けれどだからこそ、舞台の演技や、舞台での演劇のあり方というものの違いに敏感になってくれると思う。テレビや映画にはいわば演技の結果しかありません。舞台には、演技の始まりから作品としての終着まで同じ時間に体験できます。むしろ私たちの方が、いま演劇というものに興味を持つ若い人たちから教えられたいと思っています。
−−原田さんが今まで演劇をつくり続けてきたのはなぜですか? 演劇の魅力とは何でしょう?
演劇の持つ底知れない魅力にまだ気付いていない、という一言に尽きます。例えば、どうアドバイスしてもどうしようもならない俳優が居ます、彼(彼女)も悩んでいます。ある日、突然その演技が感動的なものになります、理由は全く分りません。なんでもないただの椅子があります、舞台の片隅に置くことにしました。そして突然、その椅子が舞台で行われる全てを観ていて、我々の心の全てを捉えている存在だったと気がつきます。間が埋まらないので挟んでいた虫の声があります。音響プランナーも演出のまま俳優の息に合わせて舞台に流していました。ある日その虫だけが、物語の初めから、私たちの誰もその声を耳にする以前からそこに居て、主人公の心の深層に触れていると気がつきました。例えばそんなことです。
−−最後に、これから『しんしゃく源氏物語』をご覧になる皆様に一言お願いします。
『しんしゃく源氏物語』は、演出、舞台美術、音楽、音響、照明、衣装、そしてもちろん俳優の演技も全て、ここ静岡の芸術劇場で育ち、命を吹き込まれたものです。元になった創作物語が発表されたのは千年前。それを高校演劇の第一人者榊原政常氏が、現代の視点から高校生演劇部女子生徒のための演劇にしたのが1954年。しかしここに流れる感性は私たち日本人の誰もが自らの中に認めうるものです。演出はここに示される三つの季節、冬と夏の終わりと春を、ただ一つの時期としてあるのではなく、流れ去っていく時間を一瞬にとどめたいという不可能への思いを形にしたつもりです。とはいっても榊原氏の付与した副題の通り、Fals sentimentale (註:「涙もろい喜劇」の意) としての舞台の魅力にも挑戦したつもりです。一言ではありませんね。しかし、一言で言えないのが舞台の魅力だというのが、お伝えしたい一言です。


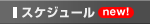





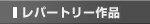


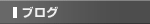

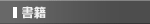
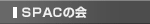
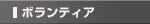




 演出家。「キンダースペース」主宰。1985年劇団キンダースペースを創立、埼玉県川口市のアトリエを拠点に活動を行う。(財)舞台芸術財団演劇人会議評議委員。90〜91年ACC(Asian Cultual Council)の招聘によりニューヨークに滞在。劇団の公演の他、多数の外部演出を手がけ、地域でのワークショップ講師や高校演劇の審査員、石川県七尾市はじめ各地市民劇団の公演企画・演出等、幅広く手がける。主な作品、E.オニール『喪服の似合うエレクトラ』他。チェーホフ『プラトーノフ』他。近代短編小説アンソロジー・芥川篇・小泉八雲篇・太宰治篇、イプセン『野鴨』『ロスメルスホルム』(以上劇団キンダースペース公演)、『しんしゃく源氏物語』、『異本 竹取物語』、『サド侯爵夫人』(SPAC)、『桜幻想』(蘭このみスペイン舞踊カンパニー、芸術祭大賞受賞)、『九番目のラオ・ジウ』、『銘々のテーブル』(俳優座)、『天国までの百マイル』、『月の真昼間』、『大つごもり』(文化座)『藪の中から芥川』(文化座)他多数。
演出家。「キンダースペース」主宰。1985年劇団キンダースペースを創立、埼玉県川口市のアトリエを拠点に活動を行う。(財)舞台芸術財団演劇人会議評議委員。90〜91年ACC(Asian Cultual Council)の招聘によりニューヨークに滞在。劇団の公演の他、多数の外部演出を手がけ、地域でのワークショップ講師や高校演劇の審査員、石川県七尾市はじめ各地市民劇団の公演企画・演出等、幅広く手がける。主な作品、E.オニール『喪服の似合うエレクトラ』他。チェーホフ『プラトーノフ』他。近代短編小説アンソロジー・芥川篇・小泉八雲篇・太宰治篇、イプセン『野鴨』『ロスメルスホルム』(以上劇団キンダースペース公演)、『しんしゃく源氏物語』、『異本 竹取物語』、『サド侯爵夫人』(SPAC)、『桜幻想』(蘭このみスペイン舞踊カンパニー、芸術祭大賞受賞)、『九番目のラオ・ジウ』、『銘々のテーブル』(俳優座)、『天国までの百マイル』、『月の真昼間』、『大つごもり』(文化座)『藪の中から芥川』(文化座)他多数。