作品について
宮城聰がオリヴィエ・ピィの話題作に挑む!
『グリム童話』の作者オリヴィエ・ピィはフランス国立オデオン座の芸術総監督で、劇作家・演出家・俳優として活躍し、世界中の注目を集める希有な演劇人です。「Shizuoka春の芸術祭2008」において日本で初めて自身の作・演出作品を上演し、翌2009年には『グリム童話』3部作の公演を舞台芸術公園「楕円堂」で行いました。チケットは発売後すぐに完売し、そのすばらしい舞台は伝説的な公演となりました。「少女と悪魔と風車小屋」はこの3部作の第1部にあたり、ピィの神秘性が詰まった傑作です。珠玉の劇詩、出演俳優の歌と楽器演奏、そして誰もが息を呑むヴィジュアル…。宮城聰の演出によって生まれ変わるSPAC版『グリム童話〜少女と悪魔と風車小屋〜』にご期待ください!
あらすじ
風車小屋に住む粉屋が森で見知らぬ男に出会い、「風車小屋の裏にあるものを3年後にくれるなら金持ちにしてやろう」と言われる。粉屋は男の提案を受け入れ、瞬く間に金持ちになる。だが男と約束したそのとき、風車小屋の裏にいたのは粉屋の一人娘だった。男は悪魔だったのだ。3年後、悪魔は風車小屋を訪れ、約束を果たすことを迫ったうえ、粉屋に命じて娘の腕を切り落とさせる。娘は悲しみのあまり放浪の旅に出て・・・。『グリム童話』の残酷な世界と、まぎれもないハッピーエンドは、現代の私たちの心をも大きく揺さぶることになるでしょう。
SPAC芸術総監督 宮城聰インタビュー
「詩の復権」を目指して
最新演出作『グリム童話〜少女と悪魔と風車小屋〜』を語る
SPAC芸術総監督に就任して4年が経とうとしている。この間、宮城は常に静岡の観客に対峙し続けて来たが、さらなる段階を模索し始めている。
宮城聰が、いま考えていることを、率直に聞いてみた。
オリヴィエ・ピィと「詩の復権」
オリヴィエ・ピィ【注1】との親交がひとつのきっかけでした。オリヴィエ・ピィの芝居は、一言で言うと「詩の復権」です。「詩が人間を変えるんだ」という確信に基づいて創られている。言葉は道具じゃなくて、それ自体が「聖なる力」を持った「人間の口から発せられるけど人間を超えたもの」であり、それが演劇の起源なんだ、という考え方です。現代の演劇シーンを見渡すと、言葉を道具として使う演劇がほとんどになっている。あるいはその逆に、言葉への“疑い”から言葉を使わなくなっている、という傾向もある。そんな中、オリヴィエ・ピィには「言葉が人間あるいは肉体とどういう関係を持っているのか」という問題意識があります。そう言ってみると、僕がク・ナウカ【注2】で「二人一役」という手法を使って、18年間追及してきたこととも同じことになるのです。ク・ナウカでは「動いてはいけなくて台詞だけ言う人」と、「台詞を言ってはいけなくて動くだけの人」という、俳優をその二種類に区別して、「言葉と身体の関係」を違和感として露呈させました。
【注1】劇作家・演出家・俳優。フランス国立パリ・オデオン座芸術総監督。詳しくはページ右のプロフィールを参照。
【注2】宮城がSPAC芸術総監督就任前に主宰していた劇団。1990年設立。現在活動休止中。
『王女メデイア』から『グリム童話』へ
ク・ナウカ時代の僕の代表作は、「Shizuoka春の芸術祭2010」でも上演した『王女メデイア』です。静岡で、SPACの演出家としての僕の理想は、『王女メデイア』で到達したクオリティを持ち、しかも子どもから大人まで何の前提もなく観にきて楽しめるという「平明さ」を持っている、そんな芝居を作ることです。今度の『グリム童話』では、その方向を模索したいと考えています。ただし『王女メデイア』と同じ手法は使わずに――。
具体的には、まずビジュアルで誰もが「きれいねえ」と感じられるものを目指したいと思います。「宝石箱のような舞台」と言ったスタッフがいましたが、そんなイメージです。また今回は、日本の演劇の長所であり弱点であるところの舞台の平面性を、極端に押し進めたらどうかと構想しています。日本の舞台は横長です。絵巻物が展示されるときには横長にひろげてありますが、日本では絵巻物を見るときのように舞台を見る。ヨーロッパでオペラハウスに行くと、平戸間席から見ても縦横比でいうと縦のほうが長い舞台を創っています。日本は逆。しかも奥行きがない。平面です。その特徴を最大限に活かしてみたらどうかなと思っているのです。
『グリム童話』で目指す、新たな演劇的試み
それから「言葉と身体の関係」で言うと、『グリム童話』では例えば次のようなことをやってみたいと考えています。俳優が、ある格好をし、その形で静止する。そのまま台詞を言います。そうすると、言葉がいかに俳優の身体に影響を与えるのか、それが眼に見えると思うのです。身体は静止している、そのぶん言葉が自立して俳優の身体を攻撃する。言葉が身体にぶつかってくるわけです。俳優の一部分が言葉として吐き出されるのではありません。中空にある言葉という独立したものが、静止している俳優に衝突するのです。このとき、いかに身体が変わるのか。怒りが込み上げるかもしれないし、喜びが湧き上がるかもしれない。「怒り」や「喜び」のように識別できる感情ですらない何かが、体の中を稲妻みたいに駆け抜けるかもしれない。ぜひ舞台を見て、そんなことを確かめてほしいと思います。もちろん普通に観ていただいても楽しい作品ですが、こういうふうに演技に注目しながら見るのは演劇だからこその醍醐味で、きっと鳥肌が立つような面白さを感じていただけると思います。「言葉が人間を変える瞬間」がいかに感動的か。
現代演劇の俳優は、この挑戦をあまりやっていませんから、新しい試みにもなるはずです。
(2010年10月)
| 主催: | SPAC (財)静岡県舞台芸術センター |
|---|


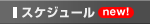





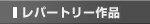


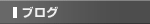

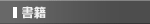
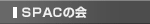
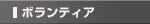


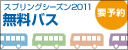



 劇作家、演出家、俳優。オデオン座芸術総監督。
劇作家、演出家、俳優。オデオン座芸術総監督。 演出家。静岡県舞台芸術センター(SPAC)芸術総監督。
演出家。静岡県舞台芸術センター(SPAC)芸術総監督。