こんにちは。SPAC演劇アカデミーで「『教養の書』を読む」を担当させていただいてます大沢由加子です。
「『教養の書』を読む」です。演劇塾なのに本を読む???しかも演劇とは全く関係のない本を???と思われるかもしれません。これまでの修了生たちには説明なしに体験してもらって「ああ、こんな感じなのか〜」と思っていただく流れでしたが、今年はなんとブログでお話しする機会を頂きました!
そこで、これから受講を検討している皆さんや、SPAC演劇アカデミーに関心をお持ちの皆さんに「『教養の書』を読む」でどんな事をやっているのか、少しだけご紹介させていただこうと思います。
「『教養の書』を読む」は夏期講習を除いて毎週水曜日19時から全編zoomで行い、戸田山和久著『教養の書』の第一部・第二部を全30回で輪読していきます。
『教養の書』は著者・戸田山和久氏の専門である哲学をメインにしながらも、古今東西あらゆる書物や映画、時には絵画や音楽などを取り上げつつ、「教養」と言われるものがいったい何であるかを検討・定義し、私たちが何故学び教養を深めていくべきなのかを考えていく内容になっています。
大学の一般教養課程の講義ノートが元になっている本なので、高校生には少し難しい言葉や内容ですし、大人にとってもあまり馴染みがない雰囲気かもしれません。「『教養の書』を読む」では、これをなるべく分かりやすく皆で楽しく読んでいくことが目標です。
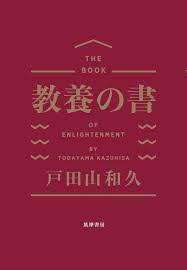
『教養の書』は演劇と直接的には何も関係がありません。ただ、クリエイティブな仕事(たとえそれが演劇であっても演劇でなくとも)に携わろうという場合にはある種の知識や学びのテクニックのようなものは必須。世の中の事を知ったり、社会を読み解く術を得ること、文化・芸術の楽しみを深めていくことなど、実際とても役に立ちます。『教養の書』はそういったことの前提となるような類の本なのです。
さて今回は折角いただいた場ですので、「『教養の書』を読む」らしく、本編の中で取り上げられているわけではないけれど、『教養の書』と関連するところのある本や映画をいくつかご紹介してみようと思います!
***
スタンリー・キューブリック
「2001年宇宙の旅」(1968・米)
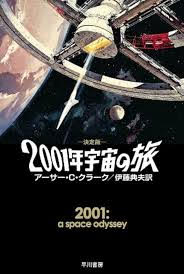
『教養の書』の序文には「私はいかにして心配するのをやめ、教養について書くことになったか」というタイトルが付いていますが、これはアメリカの映画監督スタンリー・キューブリックの「博士の異常な愛情」(1963・米)という作品のサブタイトルをもじったものと思われます。キューブリックの作品は一作ごとに異なったジャンルでどれも見応えがあるものですが、最も支持され同時代の多数の人々が見たであろう作品が、この「2001年宇宙の旅」です。
アーサー・C・クラークの同名のSF小説が原作ですが、大まかな筋書きを踏襲するのみ。この映画独自的な作品となっています。公開当時この映画のラストは賛否両論、というか「難解過ぎる」という評価が多数を占めたようですが、現代の若者の皆さんが観たらどんな感想を抱くでしょうか。気になるところです。
冒頭のR・シュトラウスの「美しき青きドナウ」に載せて展開する宇宙空間の描写はCGなどまだ無い時代のSFX(特殊撮影)の映像ですが、何度見ても素晴らしいものです。
エミリー・ブロンテ
「嵐が丘」(1847・英)
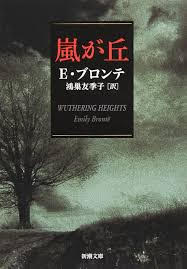
本は何を読んだら良いですか?という質問を受けることがあります。『教養の書』でも数多くの作品が紹介されますが、例えば手近なところで学校の副教材の「国語便覧」なんかに載っているような文学作品は、実際に読んでみるとどれもこれも予想だにしない新しい世界に出会えると思います。
セルバンテスの「ドン・キホーテ」やメルヴィルの「白鯨」は長すぎる気がしますが、「嵐が丘」は文学の入り口として、手を出すのにちょうど良いボリューム感。私の場合は中学時代の友人Yちゃんが「嵐が丘〜!」と興奮していたのが印象深かったものの、読んだのはそれから大分後になってから。まるで劇画タッチの少女漫画を読んでいるかのようで、古典とはいえ全く古びたところなく、のれればすいすい読めてしまう小説です。発表当時は評判が悪かったそうですが、今もってその迫力と魅力が衰えない作品です。幾度も映画化され(日本映画もあり!)、今でも時折舞台化されます。ちなみにブロンテ姉妹と呼ばれますが、お姉さんのシャーロット・ブロンテも作家で「ジェーン・エア」が代表作。
かの故・唐十郎さんも「嵐が丘」の大ファンだったということで、なるほど、妙に腑に落ちるところがあります。
ブレイディ・みかこ
「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」(2019・日)
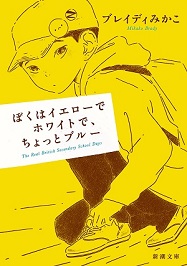
『教養の書』の後半で取り上げられる内容とかなりリンクするところがあるので、よく紹介させてもらっています。戸田山先生が『教養の書』を書いた時点ではまだ出版されていなかった本です。
イギリスで暮らすブレイディ・みかこさんの息子が中学校で体験した出来事などを中心に描かれたノンフィクション作品。現代のイギリス社会は大量の移民を受け入れた多民族国家です。異なる人種、異なる階級、異なる文化背景、多様化ということが現実的にどういった日常をもたらすのか、そういうことを身の丈レベルで伝えてくれる本です。
ちなみに、タイトルの「イエロー」「ホワイト」は人種を表すものですが、「ブルー」は ”I’m blue.”といった感じで、気落ちしている気分を表わす英語表現です。息子さんの走り書きにあったフレーズだそうですが、このタイトルってほんとに素敵なんですよね。
魚豊原作・NHK総合放送アニメ(Amazon primeやNetflixなどでも配信中。)
「チ。- 地球の運動について – 」(2024-2025・日)

ビッグコミックスピリッツで連載されていた魚豊氏による漫画のアニメ化作品。皆さんはもう見ましたか? タイトルが気になって配信で覗いてみたところ、あまりに『教養の書』とリンクする内容だったので思わず一気見してしまいました(現時点では最終話の前々回まで)。
教会による地動説の弾圧が題材ですが、これほど「学ぶこと」「自由」「知の歴史」について真っ向から描いたアニメ(漫画)がこれまであったでしょうか? さすがジャパニメーション、漫画の国・日本!を久々に実感いたしました。『教養の書』を読んだことのある人は是非見てみてくださいね(※拷問シーン多めです、苦手な人はゴメンなさい!)。魚豊さん『教養の書』読んでるんじゃないかなぁ、と思われる節多し。これを見た人なら『教養の書』をすぐに身近に感じてもらえるんじゃないかなと思います。
ただし!これは史実を元にしたフィクションではないので要注意。コペルニクスやガリレオが出てくるわけではありません(少なくとも最終話の前々回までは)。あくまでも全編架空のお話です。
***
全30回の「『教養の書』を読む」では、アカデミックな物の見方を学びます。世の中の様々な事柄や作品たちに出会います。それぞれの「好き」や「興味」を見つけたり広げたりする糸口になったら良いなと思っています。
 大沢由加子(URARA)
大沢由加子(URARA)
東京大学在学中より演劇活動を開始。俳優として小鳥クロックワーク、ク・ナウカシアターカンパニーに所属後、路上演劇や旅をしながら独自のひとり演劇を模索する。2020年よりろう者と聴者が協働する人形劇団デフ・パペットシアター・ひとみのサポートアーティスト、2024年よりアジアの舞台芸術交流活動を行うアジア・ミーツ・アジアにもメンバー参戦中。演劇外ではNHK報道局にて海外ニュース関連の翻訳の仕事もしている。
★「SPAC演劇アカデミー」とは
「世界にはばたけ、Shizuoka youth! SPAC演劇アカデミー」は、2021年度に開校した<世界で活躍できる演劇人>を目指す若者の感性を育むことを目的とした高校生対象の1年制の演劇塾です。劇場に通いながら、SPACの創作現場の“熱”をじかに感じられる環境の中で、少数精鋭の高校生たちが切磋琢磨する--そんな場をつくります。2024年度より23歳以下のオーバーエイジ枠を設置。SPACの俳優・スタッフらによる指導のもとで演劇を学び、名作戯曲の上演に向けての稽古に取り組むと同時に、教養、小論文、英語の学習にも力を入れ、思考力・対話力を身につけていきます。詳しくはこちら
★これまでのブログはこちら