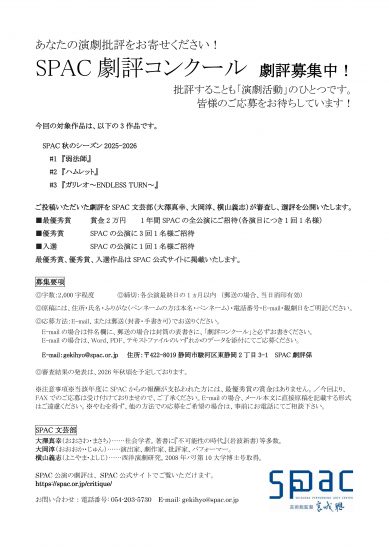パッケージ化された批判性、または「観光演劇」のアンビヴァレンス
これはきっと『The Dancing Girl of Izu』と呼ばれるべき舞台。川端康成の原作は裏切ってはいない。英語化されてもいない。それでも、わたしたちが無意識的に期待してしまいがちなステレオタイプはズラされている。学生の一人称の物語を補完するように、旅芸人の物語が対位法的に組み込まれる。いまの伊豆の映像が大写しになる。現代的なポップミュージックやダンスミュージックが騒々しいまでの大音量で鳴り響く。滑らかに連続したシーンが、断続的に、急激に、転換する。にもかかわらず、ここには不思議な納得感と説得力がある。つねに予期せぬ驚きがある。演出家の多田淳之介はわたしたちに痛快な不意打ちを食らわせてくれる。ただし、不安にまでは至らない、安全な範囲内で。
主人公である学生はいかにもそれらしい格好。学帽に袴に黒の外套。下駄に、肩掛けにしたメッセンジャーバック。しかし、彼が出会う旅芸人一座は、着物を1990年代原宿の美学で再構成したかのような、原色系のグランジ風。メイクも、歌舞伎の隈取をギャルメイクで脱構築したような、エキゾチックな日本風。そのくせ、宿の女将たちや宿泊客たちは、コミカルな昭和風。異なる時代様式が混在している。純日本的というよりも、エスニックな視点から再創造された、愉しくフェイクな日本性。
臆面もなく差し挟まれる、まったくステルスしていない「観光演劇」。川端が晩年を過ごした鎌倉の自宅を模したという軒先のような舞台、の壁面の横長の大スクリーン、に大写しになる伊豆の風景、は半実写的な背景として機能する、がところどころで劇の流れをストップさせる、観光プロモーションとして。たとえば、山道をゆく道中のシーンで、地理的な脈絡はあるとしても、物語的な必然性はない観光案内が始まる。まったくあざとく、あざとさしかないにもかかわらず、不思議なことに、余計なものが混入したという感じがしない。
それはおそらく、多田の演出が最初から、疑似的なヴァーチャル体験の共有に狙いを定めているからだろう。やや解像度の低い伊豆の山道や林道をバックに、客席のほうを向いて足踏みする俳優たちの姿は、YouTuber的な自撮り映像を思わせる。1990年代から2000年代初頭にかけて隆盛を極めたノベルゲームのようでもある。舞台がそもそもスクリーンであり、観客はその視聴者にしてプレイヤーなのだ。わたしたちは舞台に登場する予期せぬものに驚かされつつ、それらを「そういうもの」として受け入れてしまう。
にもかかわらず、わたしたちは、与えられたコンテンツの受動的な消費者になるわけでもない。劇冒頭に置かれた前口上は、すべてが作り話であることを自意識的に宣言する。『伊豆の踊子』それ自体が、旅の一座によるひとつの演目のように、物語内物語のように見えてくる。そして、作品外的なメタコメンタリーや作品内の字の文を朗読するナレーターは、軒先のような舞台に上がることはないだろう。作品内の会話文を演じる俳優たちとは別の次元があることが、視覚的にも空間的にも明示される。パフォーマンスの重層性が、物語の虚構性を担保し続ける。
しかしながら、舞台上の複数の位相はつねにつながっている。弁士的な解説者が字の文を読み上げる。すると、SPAC芸術総監督の宮城聰の二人一役の手法を髣髴とさせるように、学生や踊子が読み上げられた言葉に身体的に応える。踊子や学生はセリフを口にすることはない。しかし、過剰なまでの親密さをただよわせつつも、直接的な接触に至ることはすくないふたりの静かな身体の暖かな距離感が、川端の散文のやわらかなてざわりを具現化させる。朗読される文体と、視覚化された登場人物の関係性から、川端の抒情性を二重に味わうという、贅沢な体験。
けれども、それ以上のものがある。多田の舞台は、主人公たる学生がみずからの孤児根性を克服し、いい人だと言われたことに感動する自己憐憫的な物語以上のものになっている。自己憐憫性は、「幼いことであった」と若かりし頃を振り返る後年の川端本人の言葉を呟く弁士的ナレーターによって相対化されるだろう。川端が描かなかった物語の裏面が、旅芸人たちの悩みや苦しみ、叫びや抗議として前景化されるだろう。
その顕在化を担ったのは旅芸人の女性陣。その際たる瞬間はパフォーマンス後半部におかれたラップ。「旅芸人お断り」というローカルな立て看板に、旅芸人はリリックで応酬する。ノリのいい音楽が、腹に響くほどにビート感の強い問答無用の大音量でディスコのように響き渡る。伊豆の観光映像が流れていたスクリーンに、アグレッシブな社会批判の言葉が洪水のようにあふれ出す。
ただし、そのようなプロテストが、あくまでもポップなコンテンツとしてパッケージ化されているところに、多田の演出のとっつきやすさとお行儀の良さがある。旅芸人を見下す社会に抗議する旅芸人のラップは、パフォーマンス内パフォーマンスであるからこそ許された反抗であるようにも見えてしまう。男たちに翻弄される女たちを、健気にも、荒んだ感じにも演じ切ることは、問題の所在が社会構造にあるのか、悪辣な男ども個人にあるのかを、曖昧にしてしまう。子どもを亡くした旅芸人の体調不良は、現代に蔓延するネオリベ的な自己責任論からすれば、自業自得のように見えてしまう。俳優としての経験を積みながら旅芸人に身をやつした男も、身分違いの恋を自ら諦める踊子の諦念的な態度も、センチメンタルな共感は誘うかもしれないが、そこに社会革命を誘発するような起爆性はないだろう。多田のアダプテーションは、川端の物語を社会性に開いておきながら、そこを共感的な回路に閉鎖してしまうきらいがある。
そのほうが口当たりのよい「観光演劇」にはなる。悲恋のように描かれた学生と踊子が、悲劇のように描かれた旅芸人夫婦が、エピローグ部分で、仲睦まじいカップルとして、新たに子を身ごもった夫婦として、21世紀の現代において自撮りを愉しむ観光客になっているのは、ハッピーエンディングではある。反抗的なリリックを炸裂させていた旅芸人と、男どもに翻弄されていたその友達が、屈託なく観光している。病床に臥せっていた老人も、偏見をあからさまにしていた女将も、クイア的なパフォーマーも、幸福を謳歌している。みんながしあわせな観光ユートピア。
しかし、それがフェイクにすぎないことに、気づかされないわけにはいかない。わたしたちは「観光客」というカテゴリーに加わることでしか、新自由主義的で資本主義的なこの世界ではそれなりに裕福な消費者になることによってしか、仮初で束の間の幸福を謳歌できないのではないか。だとしたら、このような「観光客」の回路にそもそも参入することができない人々は、どうなるのだろう。
とはいえ、これだけは言っておくべきだろう。多田はエンターテイメント性を演出するために、やかましいほどの音量でダンスミュージックを流すけれど、それはおそらく、娯楽性のためだけではなく、ブレヒト的な異化作用のためでもあったのではないかという点。1990年代的なものから伝統的なものまで、2010年代20年代的なものまで、さまざまな時代の様式が節操なく召喚されるこの舞台は、きっと、ノスタルジーでも未来志向でもなく、いまここで生起しているヴァーチャルでありながらも生々しいパフォーマンスと批判的な関係を切り結ぶための意図的に導入された断絶ではなかったかという点。このギリギリの批判性を見逃す者は、多田淳之介の演出の誤解者であるはずだ。